3.我々の宇宙
3.1 宇宙膨張
ハッブルの法則は宇宙が現在膨張を続けていることを意味している。アインシュタインの一般相対性理論(
1915)を用いて宇宙の膨張する解は1922年フリードマンによって解かれた。それによると、宇宙の曲率半径の時間変化は宇宙の平均密度の大小によってことなり、![]() をハッブル定数、Gをニュートンの重力定数、とすると、現在の宇宙の密度
をハッブル定数、Gをニュートンの重力定数、とすると、現在の宇宙の密度![]() が
が
![]()
で定義される密度より大きい場合は、現在の宇宙膨張はいずれ静止し、やがて収縮に転ずる(閉じた宇宙)。また密度が![]() と少ない場合は、現在の膨張が続き宇宙は無限に膨張を続ける(開いた宇宙)。この様子をグラフに書くと次のようになる。我々の宇宙がこのうちどの場合に当たっているかを決めるには、現在の宇宙の平均密度を知ることが必要である。銀河や銀河間気体の総量から期待される密度は
と少ない場合は、現在の膨張が続き宇宙は無限に膨張を続ける(開いた宇宙)。この様子をグラフに書くと次のようになる。我々の宇宙がこのうちどの場合に当たっているかを決めるには、現在の宇宙の平均密度を知ることが必要である。銀河や銀河間気体の総量から期待される密度は![]() の
の
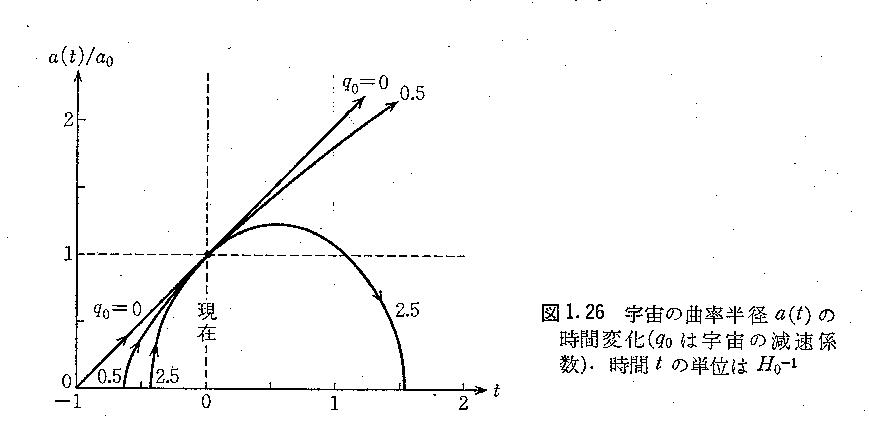
問題 宇宙の曲率半径
aの増加が一定の割合で増加するとした場合、すなわち
3.2 膨張宇宙論
膨張する宇宙を逆にたどれば、宇宙は過去に高温、高密度の状態にあり、それが断熱膨張した結果、現在の低温の宇宙に進化したと考えられる。しかし、このビッグバン宇宙論の考え方は、過去のある一時点で極端に密度の高い状態から膨張を始めたことを要求する。これは多くの人にとって受け入れがたいものだったので、ハッブルによって宇宙膨張が発見された後であっても、
1950年代までは一つの学説という位置しか占めていなかった。(当時は定常宇宙論か膨張宇宙論かというまじめな議論が行われていた。)これは過去に高温の宇宙が存在した直接の証拠が見つかるまで続いた。太陽では、水素とともにヘリウムが主な構成元素である。他の重元素、炭素、酸素などは他の星の内部で水素が燃焼して生成したものが、その星の寿命とともに星間空間に放出され、太陽の形成時に取り込まれたと考えられる。しかし、ヘリウム(全原子の質量の25%を占める。ちなみに残りの大部分である全質量の74%は水素が占める)の量は、それより重い元素(全原子の1%)に比べて非常に多いので、初代の星が形成されるより前に、高温高密度の宇宙の初期に水素原子核の核融合によって形成されたと考えられる。このことは
1940年代にガモフによって提唱されていた。
過去の宇宙が高温であるなごりの「宇宙背景放射」が
1964年、ペンジァスとウイルソンによって発見されて、膨張宇宙論は受け入れられるものとなった。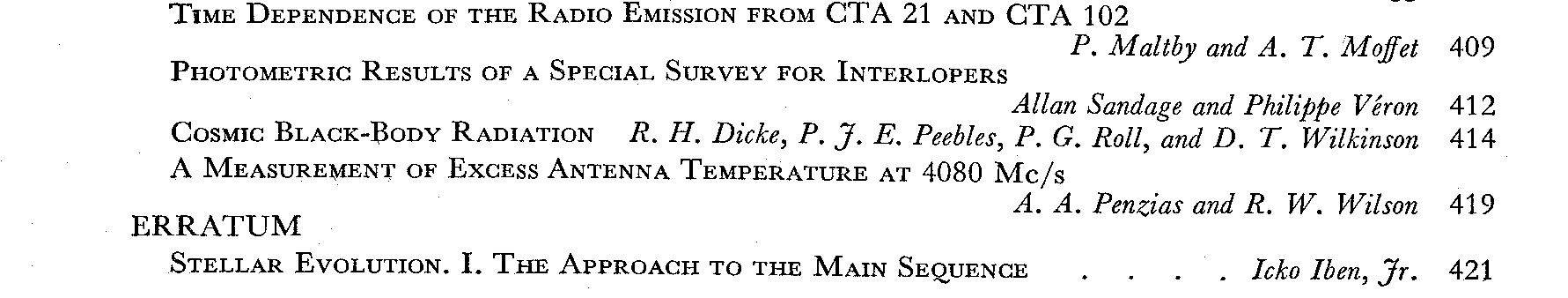
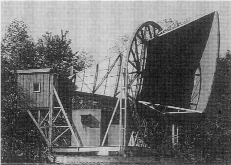
銀河などの天体が形成さえるよりも以前、宇宙が現在の密度よりも![]() 倍程度高かった過去の時点で、宇宙の物質の温度は
倍程度高かった過去の時点で、宇宙の物質の温度は
この発見によって、宇宙が過去の高温高密度の状態から膨張して形成された事が、事実によって示された。
3.4
マイクロ波宇宙背景放射の揺らぎの発見
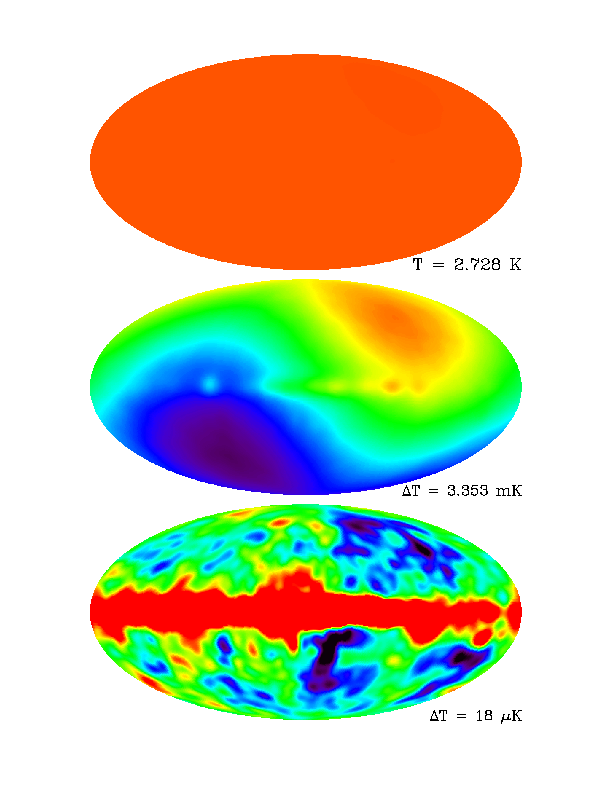
マイクロ波宇宙背景放射は一様であるという特徴を持っている(図は天球図で、背景放射の強度を濃淡で示している。一番上が一様な成分)。しかし、180度で反対称な、つまりある方向からの強度が![]() なら、その180度異なる方向からは
なら、その180度異なる方向からは![]() の強度であるような、
の強度であるような、
太陽が我々の銀河の中を約
220km/秒の速度で回転し、我々の銀河が乙女座銀河団の方向に250km/秒程度で運動している。これらを加えると太陽はほぼ400km/秒の速度で宇宙背景放射に対して運動していることになり、この運動は太陽が向かっている方向からの背景放射の波長は青い方へずらし、その反対方向からくるものは赤い方へ、 ![]()
だけずらしたことに相当している。
一番下の図はこの双極子成分をさらに除いた後に残る![]() 程度の揺らぎを示している。この図は銀河座標を用いており、赤道に相当する部分は我々の銀河の円盤を横から見た位置に相当する。したがって、赤道付近の強度の強い部分は我々の銀河の円盤部からの赤外線放射を見ている。これをさらに除くと、天球のあらゆる方向で背景放射が揺らいでいることが分かる。これが成長して、銀河の大構造
程度の揺らぎを示している。この図は銀河座標を用いており、赤道に相当する部分は我々の銀河の円盤を横から見た位置に相当する。したがって、赤道付近の強度の強い部分は我々の銀河の円盤部からの赤外線放射を見ている。これをさらに除くと、天球のあらゆる方向で背景放射が揺らいでいることが分かる。これが成長して、銀河の大構造
これらの事実から、我々は過去の高温高密度の状態から宇宙は膨張し、その中で、宇宙の大構造や銀河が形成され、現在に至っている様子を想像することができるようになっている。